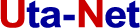



彼女の身近なスタッフに、ビートルズに造詣が深い人物がいて、彼女は自然に、このバンドに親しんでいた。作詞にも影響を与える。有名なのが、「渡良瀬橋」と「PENNY LANE」の関係だ。ともに床屋さんが出てくる(詳しくはこの曲に関して書く機会に)。
そして「わたしがオバさんになっても」ならば、「When I'm Sixty-Four」である。ポール・マッカートニーが書いたものであり、彼がティーンの頃に原型をつくり、父親がその年齢、64歳になった時、改めて完成させたものだった。特に印象深いのは、初老となった歌の主人公が、恋人に対し、「いまでも自分を必要としてくれるか?」と問いかけてる部分だ。その“女性版”として発想されたのが「わたしがオバさんになっても」なのである。
女に“盛り”などあるのか、という疑問
「いまでも自分を必要としてくれるか?」という問い掛けは、大きなヒントになったと思われる。さらにこの曲の場合、こんな具体的なキッカケもあった。実際の歌詞で言えば、[女ざかりは19だと]の部分である。それは彼女の耳に、何気なく聞こえてきた言葉だった。仕事場にいるのは、彼女より年上の男性が大半で、彼らの何気ない会話であった。しかし彼女には、聞き逃すことが出来ない表現、というか、正直、ちょっとカチンときた。果たして女の“盛り”は一生に一度きりなのか? 既にこの時、森高は成人していたこともあり、そんな疑問が湧き上がるのだった。
なぜ一方的に、男性はそんなこと決めつけるのだろうか?すかさず彼女は歌の中で、[わたしがオバさん]の頃はあなたも[オジさん]で、カッコいいこと言ってても[お腹が出てくる]と反撃している。また、それまでの自分のパブリック・イメージの重要部分であった“ミニ・スカート”も歌詞に盛り込み、歌の主人公と実際の自分とを至近にすることで、説得力の増強にも努めている。
言葉選びはユニークでも、伝えたいことは真っ当
これは森高の作品に共通することでもある。「わたしがオバさんになっても」は、女性の側から男性へ、恋の賞味期限を問い、出来ればそれが永遠であることを願う内容だ。つまり、伝えたいことはいたって真っ当なのだ。最近もユニークな歌詞を売りにするロック寄りの女性シンガー・ソング・ライターは珍しくないが、肝心なのは言葉のインパクトではなく、何を伝えたいかであることを、森高から学ぶといいのではないだろうか。
彼女の作品のなかには、他にも「ハエ男」や「テリヤキ・バーガー」など、傑作が多い。どれもいっけん、表現はユニークだが、伝えたいことは真っ当だ。しつこいようだけど、この言葉を繰り返して終りにしたい。最後に、僕が何度も取材するなかで彼女から聞いた言葉で、とても印象に残っているものを引用させていただく。
「よくいろいろな方から、“これってすごく森高っぽいよね”って言われることがあるけれど、私はけして、狙ってやったことは一度もないんですよ。かといって、積極的に“狙わないようにしよう”というわけでもない。だって、“狙わない”と決めること自体が、“狙ってる”ことなんですから」
(『月刊カドカワ 総力特集・森高千里』(94年9月号より)
