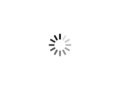Halation
曖昧を抱いて生きる僕らは、いつのまにかここにいてさ、
人一倍サイダーのガラス瓶を空け、胸のもやを晴らそうとしていた。
海鳥の声が重なって生まれた歌のようには、
いまの僕は笑えなくて、髪を撫でつけた。
光に融けてゆくイメージのなか、君を見てる――
なんにも変わんないのになにか違う笑顔の、かなわない君を。
夕立にでもなりやしないか、淡く期待してみたんだ。
言葉少ない僕らの沈黙を紛らせれば、それでよかったのにな。
臨海線のホームのベンチは錆びついて、
昔書いた君と僕の名前なんて消えちゃうだろうね。
そして天を仰いだ君に滲む、季節の終わり。
「いつかまた会えるさ」
お決まりでも信じきりたいと思った。
人一倍サイダーのガラス瓶を空け、胸のもやを晴らそうとしていた。
海鳥の声が重なって生まれた歌のようには、
いまの僕は笑えなくて、髪を撫でつけた。
光に融けてゆくイメージのなか、君を見てる――
なんにも変わんないのになにか違う笑顔の、かなわない君を。
夕立にでもなりやしないか、淡く期待してみたんだ。
言葉少ない僕らの沈黙を紛らせれば、それでよかったのにな。
臨海線のホームのベンチは錆びついて、
昔書いた君と僕の名前なんて消えちゃうだろうね。
そして天を仰いだ君に滲む、季節の終わり。
「いつかまた会えるさ」
お決まりでも信じきりたいと思った。
RANKING
For Tracy Hydeの人気動画歌詞ランキング